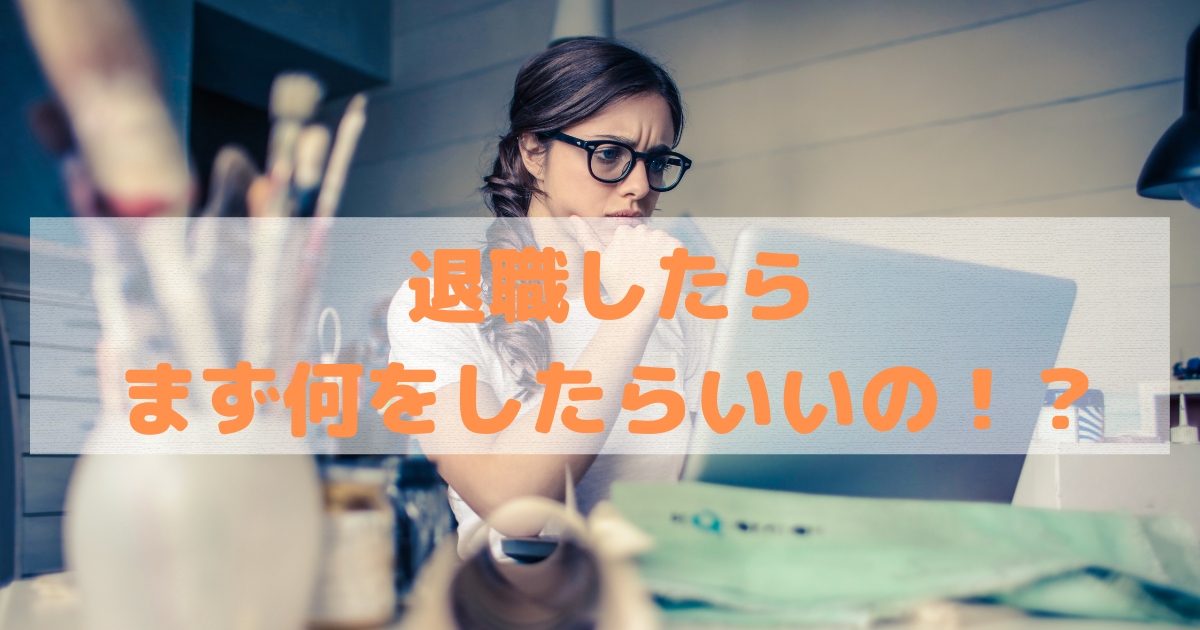会社に勤めていると、社会保険や年金、税金の手続きなどは、人事や総務の担当者が行ってくれる場合が一般的です。
しかし、会社を退職後の手続きは、基本的にはすべて自分で行わなければなりません。 手続きを怠っていたり忘れてしまうと、思わぬ不利益を被ってしまうケースもあります。
本記事では、退職後に次の職場にすぐ就職が決まっている場合と、まだ決まっていない場合で、どういった手続きが必要か解説します。
退職する時に会社から受け取る書類 退職した際は、会社から受けとるべき書類がいくつかあります。
①源泉徴収票
所得税の計算をするために使用します。会社からすべての給与が支払われた後に発行されるため、一般的には最終の給与明細と一緒に郵送されます。
②雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していた場合は、会社が保管しています。 離職票とあわせて受け取る場合が多いですが、紛失してしまった場合は、ハローワークで再発行が可能です。
③離職票
雇用保険の失業給付を申請するために必要です。 次の就職が決まっていて、失業の手続きをしない場合は必要ありません。退職日以降に会社が発行するため、多くの場合は後日郵送されます。
④年金手帳
厚生年金に加入していて、会社に年金手帳を預けている場合は返却してもらいます。
なお、2022年4月以降は年金手帳の新規発行が廃止になったため、年金手帳の受け渡しが不要です*¹。
退職日の翌日に次の会社に入社する場合の手続き (最終出勤日ではなく、書類上の)
退職日の翌日に、すぐ次の会社へ入社する場合、つまり離職期間がない場合は、自分で行わなければならない手続きは、基本的にありません。 転職先の会社から求められる書類を揃えて提出しましょう。
転職先に提出が必要な書類例 源泉徴収票 雇用保険被保険者証 健康診断書、扶養控除等申告書、マイナンバーなど 退職前の会社で、企業型確定拠出年金に加入していた場合は注意が必要です。
確定拠出年金を移換して加入できるかどうか、転職先の担当者に確認しましょう。 もし移換できない場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換を検討しましょう。本手続きをしないと、国民年金基金連合会に自動的に移換され、資産運用ができなくなります。 移換の手続きは、資格喪失日(退職日の翌日など)の翌月から5か月以内です。多くの金融機関が対応しているので、相談しましょう。
退職後、転職までに離職期間がある場合の手続き 次の仕事が決まっていない場合や、退職日から次の入社日までに1日でも期間が空くと「離職」となるため、保険や年金など、自分で手続きが必要です。
健康保険 退職前に会社で健康保険に入っていた場合は、以下の3つの方法があります。
退職前から国民健康保険へ加入していた場合は、手続き不要です。
①「任意継続健康保険」を利用
今までと同じ健康保険を最大2年間継続できます。資格喪失日から20日以内に申請書類の提出が必要です*²。 継続加入には一定の要件があることと、今まで会社が負担していた保険料も自分で払うことになります。
検討する場合は、早めに加入していた健康保険会社に相談しましょう。
②「国民健康保険」に加入
退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市町村の国民健康保険の窓口で手続きをします*³。 提出が必要な書類は、市町村や国民健康保険組合のホームページで確認ができます。
③ 「家族の健康保険(被扶養者)」に加入
家族が健康保険に加入している場合は、被扶養者として加入できる場合があります。 家族が加入している健康保険組合に問い合わせてみましょう。
年金
退職前に厚生年金に入っていた場合は、退職後、以下のいずれかの手続きが必要です。
① 国民年金に加入する
退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市町村の国民年金の窓口で手続きをします*⁴。
退職日がわかる書類、基礎年金番号がわかるもの、本人確認ができるものを持っていきましょう。
② 配偶者の扶養に入る
配偶者の扶養に入る日から14日以内に、扶養者の勤務先へ申し出れば、会社で手続きを行ってくれます*⁵。
失業給付
雇用保険に加入していて、病気や怪我など、すぐに働けない状態でなければ、失業給付を受け取れます*⁶。
離職票が届いたら、雇用保険被保険者証と本人確認書類、印鑑、証明写真2枚、本人名義の普通預金通帳かキャッシュカードを持って、ハローワークの雇用保険の窓口へいきましょう。
退職後の税金に関する手続き
最後は、税金に関する手続きです。本手続きを怠ると、延滞金が発生する場合もあるので忘れずにおこないましょう。
① 所得税
退職した年の年末までに再就職が決まれば、前職の源泉徴収票を再就職先に提出すると、会社が年末調整で手続きしてくれます。 年内に就職が決まらなければ、自分で確定申告をする必要があります。確定申告の期間は、毎年2月から3月と決まっています。必要な書類や手続きの方法など、最寄りの税務署で早めに確認をしておきましょう。
② 住民税
住民税は、会社で働いているときは給与から天引きされますが、退職すると自分で納税しなければなりません。
再就職が決まっていない場合は、自宅に納付書が届くので、納付期限までに納付しましょう。
まとめ
退職後の手続きは、離職期間の有無で異なります。
離職期間がある場合は、自分でやらなければならない手続きが多くあるため、忘れないように書き出しておきましょう。
わかりにくい手続きや必要書類は、本記事で紹介した窓口などに相談して進めてください